京都大学大学院 文学研究科
美学美術史学研究室
 教員・大学院生の紹介 更新:2010年5月6日
教員・大学院生の紹介 更新:2010年5月6日
吉岡 洋(よしおか・ひろし)
教授【美学芸術学】
西洋近・現代の美学・芸術学(カント、アドルノ)から出発し、1990年代後半以降は現代科学の与える文化的インパクトや、デジタル・メディア、電子的ネットワークという新たな環境下における表現活動、文化一般について、著作活動を行ってきました。社会的実践面では、現代美術やメディアアートの展覧会企画、批評誌の編集や地域の出版プロジェクトにもかかわってきました。現在日本記号学会編集委員長として『新記号論叢書 セミオトポス』を担当しています。
詳しいことは、個人ウェブサイトSpace in CyberSpaceを参照してください。ぼくに関係するニュースや予定、これまでの著作・活動などを掲載しています。著作の電子版やオランライン・テキストも読むことができます。

 業績・活動は、研究者総覧データベースを参照
業績・活動は、研究者総覧データベースを参照
中村 俊春(なかむら ・としはる)
教授【西洋美術史】
主たる研究分野は、16-17世紀のフランドルおよびオランダ絵画で、特に関心を寄せているのは、ルーベンスおよびヴァン・ダイクとイタリア美術との関係、ならびにルーベンスの女性表現の問題である。また、鑑定およびアトリビューションをめぐる諸問題や、科学調査法の可能性と限界に関して、実践的かつ理論的な研究を進めている。芸術家と美術を取り巻く社会環境との関連にも興味があり、最近、芸術家と批評家、展覧会制度の確立と芸術家の戦略、といった問題の考察に着手したところである。
Email:

 業績・活動の詳細は 研究者総覧データベースを参照
業績・活動の詳細は 研究者総覧データベースを参照
根立 研介(ねだち・けんすけ)
教授【日本美術史】
近年取り上げている主な研究テーマは以下の通りである。
1. 仏師論:仏像や肖像彫刻を造る仏師の工房組織の実態の解明や、仏師という特殊な技術者集団がどのような社会的な地位を占めていたかなどを解明する。
2. 肖像論:肖像をめぐる像主、制作者、受容者の関わりといった問題を、肖像彫刻を中心に論じる。
3. その他:仏像の制作、機能、受容に関わる問題。
Email:
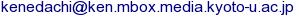
 業績・活動の詳細は研究者総覧データベースを参照
業績・活動の詳細は研究者総覧データベースを参照
平川 佳世(ひらかわ・かよ)
准教授【西洋美術史】
主な研究分野はルネサンス美術です。特に、デューラーを中心とするドイツ・ルネサンス美術、および、神聖ローマ皇帝ルドルフ二世のプラハの宮廷における北方ルネサンス美術の受容の問題に取り組んできました。また、イタリア美術と北方ヨーロッパ美術の交流にも興味があります。現在、イタリアにおける北方絵画愛好や北方画家とイタリア人画家の競合について、16世紀に流行した銅板油彩画という特殊な絵画形態に着目して調査研究を行っています。芸術作品を、その美的特質に加えて、制作当初の用途や受容空間といった様々な側面から把握するよう努めています。
Email:

 業績・活動の詳細は研究者総覧データベースを参照
業績・活動の詳細は研究者総覧データベースを参照
大学院 博士後期課程
"haptic"を中心とした感覚論、及びメディアアート論
○西嶋 亜美(にしじま・あみ)
十九世紀フランスにおける絵画と演劇の相互関係の研究
○深田 祐輔(ふかだ・ゆうすけ)
映画における「でたらめなつなぎ」の問題について
○倉持 充希(くらもち・みき)
ニコラ・プッサンと同時代のローマの画家たちの物語画に関する研究
○尾崎 恵子(おざき・けいこ)
エル・グレコの作品を中心とした17世紀スペイン祭壇画の研究
○柳 承珍(りゅう・すんじん)
日本仏教美術史
○萩原 沙季(はぎわら・さき)
鈴木其一の屏風絵について
○江尻 育世(えじり・いくよ)
15-16世紀のフィレンツェ派を中心としたイタリア美術
○加藤 隆文(かとう・たかふみ)
プラグマティズムと美学
○Diaz Sancho Ivan(ディアス サンチョ イヴァン)
寺山修司の芸術観における「スポーツ」及び「見せ物」
大学院 修士課程
○加藤 祥平(かとう・しょうへい)
日本近世の絵画
○楠本 愛(くすもと・あい)
現代美術作品への理論的考察及び批評実践
○高橋 早紀子(たかはし・さきこ)
日本仏教美術史
○野村 文乃(のむら・あやの)
浮世絵版画について
○浅井 佑太(あさい・ゆうた)
19世紀末~20世紀初頭のドイツ音楽
○佐々木 玄太郎(ささき・げんたろう)
中国の現代美術
○朴恩永(ぱく・うにょん)
韓国と日本の映画における映画美学の研究
大学院 博士後期課程 (詳しい紹介・研究業績)
○太田 純貴(おおた よしたか)
hapticを中心とした感覚論、及びメディアアート論
haptic(仏: haptique)の概念は、例えばドゥルーズの感覚論においては「触感的」「触視的」などと訳される。感覚概念を単純に区分された五感のエコノミクスとして捉えるのではなく、横断的な感覚のあり方であるhapticの概念に注目し、それが持つ意味、可能性さらには身体との関係性を追及することが本研究の
目的である。また、このような感覚と密接に結びつくと思われるメディアアートに注目し、生理学・認知科学などの知見を取り入れた多角的な視点から、「メディアアート」という概念の生成・変様過程の検討、さらにはメディアアート概念の再考を目指す。
<業績>
●修士論文
・「ドゥルーズの感性論―「haptique」という言葉を中心に―」
京都大学大学院文学研究科2007年3月
●口頭発表
・「インターネットにおける『接触』について」、『第一回視聴覚文化研究会』、京都(同志社大学)、2005年9月
・「ドゥルーズの感性論-<haptique>という言葉を中心に-」、『第七回視聴覚文化研究会』、京都(京都大学)、2007年
・「ドゥルーズの感覚論―<haptique>という概念を中心に―」第58回美学会全国大会(北海道大学)、2007年10月
・「どもるということ」、『第十四回視聴覚文化研究会』、京都(京都大学)、2008年12月
・「どもるということ」、『日本記号学会第29回大会』、神奈川(東海大学)、2009年5月
・「2009アルス・エレクトロニカレポート」、京都(京都大学)、2009年10月
・「ヴィデオ試論」、『第八回京都美学美術史学会研究大会』、京都(京都大学)、2009年12月
●翻訳
・ エルキ・フータモ「家庭こそメディアの場所である―家庭内メディアの考古学」
(所収書誌名:京都大学グローバルCOEプログラム「親密圏と公共圏の再編成をめざすアジア拠点」2008-2009年度国際共同研究「東西の美術における家庭、女性、子供の表象」最終成果報告書、2010年3月発行)
・ ディヴィッド・ジェローム・パトナム「スイスの視覚教育―クレー+ペスタロッチ」、『美術フォーラム21』、醍醐書房、2010年5月刊行
●論文
・「ドゥルーズの芸術論における時間と身体の問題についての一考察」『京都美学美術史学』第7号、2008年、67-95頁
・「Haptiqueとは何か――『感覚の論理を中心としたドゥルーズの感覚論』」、美学232号、2008年夏、29-43頁
○高嶋 慈(たかしま めぐみ)
現代美術における言語と視覚性の関係について
現代美術、特にマルセル・デュシャンの作品やテクストを中心に言語とイメージや視覚性の関係について考察する。また、ジャン=フランソワ・リオタールの「フィギュール」の概念をもとに、美学面からの考察も試みたい。
<業績>
●口頭発表
「Relational Artにおける「関係性」の批判的考察」第58回美学会全国大会(北海道大学)、2007年10月
○鄭 賢娥(チョン ヒョナ)
1950年代以降、前衛美術の傾向についての研究ー<芸術においての政治性とは何か>
1950年後半、前衛グループにおいての芸術と政治性の共存という問題について研究を行う。特に、九州派の政治的観点を探ることで他のグループとの特異を考察する。
<業績>
●修士論文
「1950年代リアリズムの再考ー<ニッポン展>とその周辺」京都大学大学院文学研究科、2008年3月
○西嶋 亜美(にしじま あみ)
十九世紀フランスにおける絵画と演劇の相互関係の研究
ドラクロワと同時代のフランスにおける歴史画・物語画と演劇との関係を考察する。
<業績>
●口頭発表
「ドラクロワ作 ≪墓地のハムレットとホレーシオ≫ ―フランスにおけるシェークスピア受容の観点から―」美術史学会西支部例会,平成21年9月19日, 於京都工芸繊維大学
●論文
「ドラクロワによる「挿絵」連作《ファウスト》 ―複数の着想源と技法革新の統合の試み―」(『京都美学美術史学』 第9号(2010年4月発行)に掲載、141-172頁)
●修士論文
『ウジェーヌ・ドラクロワ作《墓地のハムレットとホレーシオ》についての一考察―フランスにおけるシェークスピア受容との関連から―』京都大学大学院文学研究科、2009年
○深田 祐輔(ふかだ ゆうすけ)
映画における「でたらめなつなぎ」の問題について
映画の制作と受容において、音を含めたイメージは如何に連鎖しているのか、また、そもそもなぜ人はイメージを「連鎖」させようとするのかを、ドゥルーズ『シネマ』を出発点として、歴史、美学、哲学的視点から考察する。また、連鎖しないイメージとはいかなるものか、またそもそもそれは可能かといった問題についても検討する。
<業績>
●論文
「映画における『でたらめ」なイメージ連鎖について」 『京都美学美術史学』第9号、2010年
○倉持 充希(くらもち みき)
ニコラ・プッサンと同時代のローマの画家たちの物語画に関する研究
<業績>
●卒業論文
「ニコラ・プッサンの物語画の構成をめぐる考察―1630年代の3作品にみる時間表現―」 京都大学文学部、2007年
●修士論文
「プッサン作《羊飼いの礼拝》―1630年代前半の「キリスト降誕」に関連する作品の研究―」 京都大学大学院文学研究科、2009年
●口頭発表
「プッサン作《羊飼いの礼拝》に関する一考察―デューラーの版画に基づく「新奇な」主題表現への志向―」 第62回美術史学会全国大会(京都大学)、2009年5月24日
●論文
「アメデオ・ダル・ポッツォのためのモーセの物語画連作―プッサン、コルトーナ、ロマネッリの競演―」 『京都美学美術史学』第9号、2010年
○尾崎 恵子(おざき けいこ)
エル・グレコの作品を中心とした17世紀スペイン祭壇画の研究
<業績>
●修士論文「エル・グレコ作「ドニャ・マリア・デ・アラゴン学院の主祭壇」の再構成―画家の制作環境を手がかりに―」京都大学大学院文学研究科、2009年
●論文「アロンソ・デ・オロスコの幻視に基づくエル・グレコの作品解釈―ドニャ・マリア・デ・アラゴン学院の主祭壇を中心に―」『京都美学美術史学』第9号、2010年
○柳 承珍(リュウ スンジン)
日本仏教美術史
特に、東アジア美術史の視点を踏まえ、日本の釈迦如来像の受容と展開について考察する。
<業績>
●修士論文
「韓国四面仏像の研究」、ソウル大学(Seoul National University, Seoul)、2006年8月、韓国語
○萩原 沙季(はぎはら さき)
鈴木其一をはじめとする琳派と呼ばれる画家について
琳派と呼ばれる画家について、中でも鈴木其一の人物画について考察したいと考えている。
○江尻 育世(えじり いくよ)
15-16世紀のフィレンツェ派を中心としたイタリア美術
<業績>
●修士論文
「ボッティチェッリ作《柘榴の聖母》:交錯する聖と俗」 2011年3月 京都大学
●口頭発表
「ボッティチェッリ作《柘榴の聖母》を巡る一考察」第64回美術史学会全国大会(於 同志社大学) 2011年5月21日
○加藤 隆文(かとう たかふみ)
プラグマティズムと美学
デューイの芸術論のみならず、パースの思想を参照することで、プラグマティズムの立場から見た美学を広い視野で考察したい。
<業績>
●修士論文
「パースのプラグマティズムに基づく美学ー脱人間主義的美学の試み―」京都大学大学院文学研究科、2011年3月
●口頭発表
「パースのプラグマティズムと美学」第60回美学会全国大会(東京大学)、2009年10月
「不死性の問題―パースを手がかりに」記号学会分科会―特集「タイムマシン/タイムトラヴェル」(京都大学)、2011年1月
「パースのプラグマティズムに基づく脱人間主義的美学の試み」日本哲学会第70回大会(東京大学)、2011年5月
○Diaz Sancho Ivan(ディアス サンチョ イヴァン)
寺山修司の芸術観における「スポーツ」及び「見せ物」―1960-70年代の前衛をめぐって―
<業績>
●修士論文
『オルフェウスの軌跡:詩人シルロットに於ける超越性』バルセロナ自治大学 (Universitat Autonoma de Barcelona),
2007
大学院 修士課程 (詳しい紹介・研究業績)
○加藤 祥平(かとう しょうへい)
日本近世の絵画
日本の近世前半を主とし、画師と公家や武家、僧侶などとの文化的交流の観点から考察を進める。
○楠本 愛(くすもと あい)
現代美術作品への理論的考察及び批評実践
研究分野は20世紀後半から現在までの芸術作品と諸動向です。特に1970年代以降、美術領域における写真の受容に関心があります。
○高橋 早紀子(たかはし さきこ)
日本仏教美術史
仏像を通して、その思想的背景や信仰の在り方について考察したいと思っている。特に平安初期について研究する。
○野村 文乃(のむら あやの)
浮世絵版画について
現在、歌川豊春・豊国・豊広の浮絵や美人画の背景にみられる遠近法表現について考察していきたいと考えている。
○浅井 佑太(あさい ゆうた)
19世紀末~20世紀初頭のドイツ音楽
○佐々木 玄太郎(ささき げんたろう)
中国の現代美術
現在、中国という特殊な環境下における芸術のあり方(芸術観、受容のされ方など)に関心を持っている。
○朴 恩永(ぱく うにょん)
韓国と日本の映画における映画美学の研究